
「全員広報」の文化はどうつくられた?LayerXの石黒さんが語るオウンドメディア戦略
オウンドメディアを立ち上げた目的や、運営を続けていくための成功ポイントについて、企業担当者にインタビューするイベント「実践企業に学ぶ オウンドメディア成功の秘訣」。
今回は株式会社LayerXのCCO(Chief Communication Officer)として、人事・広報の両方を担当する石黒卓弥さんにお話を聞きます。LayerXといえば、たくさんの社員がSNSで発信する「全員広報」の文化でお馴染み。その文化を築き、継続するうえで大切にしてきたことを伺いました。
多くの社員が発信し続けるための「フィードバック」
——LayerXという会社と、石黒さんの立場について教えてください。石黒さんは、人事と広報の両方を見ているのが特徴ですよね。
石黒さん(以下、石黒) LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに、複数の事業を手がけているスタートアップ企業です。現在は3つの事業を展開していて、法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AI-SaaS「バクラク」事業と、Fintech事業、AI・LLM事業になります。
今は360人ほどのメンバーがいる当社ですが、私が入社した2020年5月当時は、まだ会社全体で28人ほどの規模。エンジニアや事業を見るメンバーが25人と、コーポレート業務を担当するメンバーが3人の状況でした。その頃は広報も外部委託だったので、私が人事と広報の両方を担当することになったのです。
——それからは、いわゆる「採用広報」の役割をされていますね。人事と広報をセットで見ること、そして当時はまだ馴染みのなかった「採用広報」という役割を担うことに戸惑いはありませんでしたか。
石黒 それはなかったですね。というのも、私は前職がメルカリで、現取締役会長の小泉文明さんが「採用広報」といった言葉を早くから使いはじめていました。なので戸惑いはなく、むしろ「人事と広報を一緒にやらないと大変だろう」とさえ思っていました。
なぜなら、採用活動は「どうやって会社のことを知ってもらうか」に尽きるからです。認知度の高い会社に行きたい人が多いのは当然ですし、認知が上がることで採用が加速します。
メルカリも今でこそ国民的サービスですが、私が入社した2015年は、まだ現在のような認知はありませんでした。そのため、いかに「熱量ある1人の応募」を獲得していくか、その1人に刺さる発信をしなければならなかったんです。
また、この10年、20年をみると、個人の価値観による意思決定が尊重される社会になってきました。そのなかで「この会社に入りたい」と思ってもらうためには、企業が積極的に情報を届けて、共感してもらう広報活動が必要だと感じています。
——LayerXの特徴である「全員広報」の文化が気になっています。採用ページをみても、noteからPodcast、connpass、エンジニアブログなど、本当にたくさんのコンテンツが並んでいますよね。こういった文化をどう醸成していったのでしょう?
石黒 基本的には「やりたい人がやる」スタンスで、こちらから社員に強く「発信してください」と言うことはありません。
私がLayerXに入社した頃の会社規模では、何も言わなくてもSNSをはじめる社員が多かったです。なぜなら、何かを発信しないと会社の認知度が上がりませんから。SNSはスタートアップにとってひとつの生存戦略であり、数少ない“使える武器”。そこでリスクを避けるよりは、認知の拡大を優先したのだと思います。
問題は会社の規模が100人、200人と大きくなったときですね。社員がふえても「みんなが発信する文化」を維持し続けられるかは、なかなか難しいと感じます。

「メディアブックマーク」は、LayerXの今がわかる!コンテンツたち。
——LayerXではそれを維持し続けていますね。何か秘訣はありますか?
石黒 私たちが大切にしたのは、発信してくれた人への感謝です。同時に「タイトルをこうするとさらに読まれると思うよ」といったサポートをしています。
あわせて当社で行ったのは、発信の場をつくることでした。たとえば2021年10〜12月には、初めてのアドベンドカレンダー(アドカレ)を実施しましたね。以降も、3〜4月、6〜7月と開催しています。アドカレは12月に実施する会社が多いので、あえて違う時期に行って、読まれる確率を高めています。
——こういう場を設けることで、みんなが発信に参加するきっかけをつくったと。
石黒 イベントとして毎日発信をしていると、「私も書こうかな」という人が出てきます。またアドカレをすると、今まで続いてきたバトンを落とせないので、誰かがつなごうとする連帯感も生まれてきました。
そのほかに大切なのが、記事の拡散です。弊社CEOの福島や私は、多少なりともフォロワーがいますので、毎日社員のnoteをこまめにシェアしました。すると、スキが100以上つくようなヒット作が出てきます。こういうヒット作が出ると、今度はメンバーのnoteを読んで応募してくださる採用候補者が現れるんです。
そういった場合は、「〇〇さんのnoteを見て、当社に応募してきた方がいました」と社内のSlackで共有します。すると執筆した本人は、誰かの人生に影響を与えられたことをとても喜びます。こういうサイクルをコツコツと続けてきました。
——なかには文章を書くのが苦手な方もいると思いますが、そういう方にはどのようなアプローチをしていますか?
石黒 あくまで無理に書いてもらうことはしません。ただ、文章が苦手だけど発信したい人には、ドキュメントでフォーマットをつくって質問を4〜5つほど渡して、それぞれ300字くらいで回答してもらいます。すると、それだけで1つのブログになるんですよね。
ちなみに、noteについては「記事」という言葉をなるべく使わないようにしています。「記事を書く」と伝えるとハードルが高くなるので(笑)。noteは「noteを書く」と言っています。
堅くなりがちな会社のイメージを中和させた「エモカレ」
——これまでに手応えのあった企画はありますか?
石黒 「LayerXエモカレ」ですね。エモカレとは「エモいお気持ちカレンダー」の略で、会社のメンバーがどんな想いで働いているかといった“エモい面”をインタビューで引き出していくnote企画です。
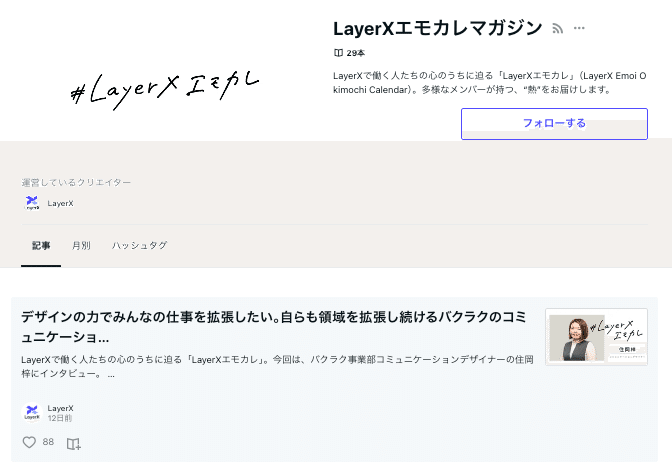
noteが集約されている。
石黒 この企画を立ち上げた背景として、うちの会社は技術やコンピュータサイエンスのイメージが強すぎるのではないか、という想いがあって。KPIなどの数字ばかりをみて、評価する会社に思われていないかと(笑)。そこで社員のエモさを伝えるnoteを投稿していこうと考えたんです。
——会社のイメージを中和させる戦略で生まれたんですね。
石黒 広報は、会社が今どう見られているかを中立的に理解する能力が重要だと思っています。役所に行くと、よく「広報広聴課」という課がありますが、まさに“広聴”の部分です。企画を考えるときもその点を意識していて、エモカレも当社の持つイメージを考えるなかで生まれました。
先ほど話したアドカレは各メンバーが個人noteに書いていますが、エモカレはLayerXの公式noteで展開しています。社内のメンバーがインタビューや撮影、ライティング、編集などを行っていますね。
効果測定はしないからこそ、社内や経営陣に伝えることが大切
——これらの活動の効果測定はどうしていますか?
石黒 よくその質問をいただくのですが、基本的に効果測定やKPIはほとんど意識していません。それらを意識すると、どうしても答えを取りに行くような施策が増えてしまうので。
ただし効果測定を意識しない一方、こうした取り組みが会社にどう役立っているのか、細かく社内や経営陣に伝えていますね。
——具体的に、どういうことを社内に伝えるのでしょうか。
石黒 たとえば、「〇〇のnoteが、記者の間で反応がよいです」と伝えるなど、数字では見えない、ひとつひとつの発信が残したインパクトや反応を経営陣に届けるようにしています。
SNSの発信は何を効果とするかの判断が難しいからこそ、こういうコミュニケーションで経営陣の信頼を得ておかないと、ときに一瞬の感覚でこの活動をやめる判断があるかもしれません。そういうことが一度でも起きると、広報チームの活動も萎縮してしまいます。
バズった数字を経営側に伝えるのは慎重になるべきで、“バズ”を成果にしすぎると、その後またバズを求められるようになっていきます。どんな目的があり、そのためにどういう活動をしているのか、この点をきちんと伝えることが大切ではないでしょうか。
——ちなみに、今の課題として感じていることはありますか?
石黒 スタートアップのなかでは、徐々に認知していただける会社になってきましたが、その認知を日本全国のみなさんが知っているところまで広げるには、まだ時間も投資も必要だと思っています。そこでnoteとは別に、「YOSORO(ヨーソロー)」というメディアをつくりました。

石黒 このメディアは、日本のデジタル化を前に進めることや、挑戦者を応援することをテーマにしており、さまざまな企業やプロジェクトを取り上げています。一見すると、LayerXが運営しているメディアだとわからないほど、当社の事業から離れた記事も多いです。
——オウンドメディアには、自社を語るものもあれば、自社や事業からテーマを広げて発信するものもあります。こちらは後者ですね。
石黒 そうですね。私たちスタートアップは常に「挑戦」している企業なので、その「挑戦」をいいものだと思っていただきたいと考え、それをメディアのテーマにしました。同じく、私たちが挑むデジタル化への意義もこのメディアで感じてもらえたらと思っています。
転職活動で大切なのは「なぜその会社に行くのか」「その会社で何がしたいのか」というストーリーです。当社に応募してくださる方が、はっきりとそれを家族や知人に言える状況にしてあげないといけません。ですから、いろいろな角度からストーリーをつくり、発信することを意識していますね。
最初の一歩目は「2週間で3ネタ」がおすすめ
——LayerXのような全員広報の発信を自社でやりたいと思ったとき、社内の理解をどう得ていけばよいでしょうか。
石黒 まずはトップの理解を得ることです。この活動を「経営者の仕事」「経営者のやるべき宿題」にしなければ、社内の理解は進みません。
なぜなら、社員にとって本業ではない「発信」を、会社として評価・サポートしなければならないからです。きっと外部のプロの方が文章を書いたほうがクオリティーは高くなる。それでもあえて社員が書くことに意味があり、活動を続けることで、採用や会社の認知が上がっていくのです。それを会社全体で理解するには、トップの協力が不可欠だと思っています。
——ほかの企業でも会社のYouTube活動を社長みずからがnoteで紹介したことで、社内の理解が広まったという話がありました。トップの理解を得ることはやはり大切ですね。
石黒 その一方で、社員一人一人については、何かしらSNSで発信してみてほしいですね。特に大企業は、社員のSNS発信に慎重なケースが多く、控えている人も多いでしょう。ですが、自分でも出来るところまでやってみる。すると誰かが反応してくれて、新しい動きにつながるかもしれません。
——今のお話に通じると思いますが、明日からSNSで何か発信しようと思ったとき、最初の一歩目はどうすればよいでしょうか。
石黒 たとえばnoteをはじめるとき、頭をよぎる不安は大きく2つあると思います。「続かないこと」と「読んでもらえないこと」です。対策として、まずはネタを3本ためて、その3本を2週間のうちに公開してみてはいかがでしょうか。
私の経験上、2週間で3本アップすると、その後1ヶ月書かなくても「いつも読んでいます」と言ってもらえます(笑)。おそらくそのペースだと「定常的に発信している人」という印象になりやすいです。なおかつ、3本ほど出せばどれかよい反応をもらえるかもしれません。
——それならはじめやすいですね。みなさんもぜひ参考にしていただけたらと思います。本日はありがとうございました。
▼イベントのアーカイブ動画は以下からご覧いただけます。
登壇者プロフィール
石黒 卓弥さん
株式会社LayerX CCO(Chief Communication Officer)

株式会社NTTドコモに新卒入社後、マーケティングのほか、営業・採用育成・人事制度を担当。また、事業会社の立ち上げや新規事業開発なども手掛ける。2015年1月、当時まだ60名だった株式会社メルカリに入社し人事部門を立ち上げ、5年で1800名規模までの組織拡大を牽引。採用広報や国内外の採用をメインとし、人材育成・組織開発・アナリティクスなど幅広い人事機能を歴任。2020年5月、株式会社LayerXに参画。人事と広報領域を担当している。
モデレーター
徳力 基彦
noteプロデューサー/ブロガー

「実践企業に学ぶ オウンドメディア成功の秘訣」シリーズのイベントレポートのバックナンバー公開中です。あわせてお楽しみください。
noteの法人向けプラン note proの詳細はこちら
note proでの情報発信、活用方法に疑問や不安はありませんか?
担当者が、貴社の課題とnote proの特性を踏まえて、活用方法や参考事例をご提案いたします。下記からお気軽にオンライン個別相談をお申し込みください。


interviewed by 徳力基彦 text by 有井太郎


